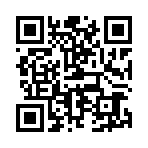おせち料理 弐の重です。
2017年11月02日
こんにちは、エクステリア キシシタ です♫
11月に入りましたね!
今年も残すところ・・・あと2か月。
10月30日に発信しましたおせち料理の第2段
弐の重のまめ知識です

弐の重[焼き物]
縁起のいい海の幸が中心です。
【ぶり】
ぶりは大きさによって名前が変わる出世魚。ぶりで立身出世を願います。

【鯛】
「めでたい」にかけています。
姿もよく味もよい鯛は、江戸時代から「人は武士、柱は檜(ひ)の木、魚は鯛」といわれ、めでたい魚として祝膳には欠かせないものとされています。

【海老】腰が曲がるまで長生きできるように。

参の重[煮物]
山の幸を中心に、家族が仲良く結ばれるよう煮しめます。
【れんこん】
穴があいていることから、将来の見通しがきくように
【里芋】
子芋がたくさんつくことから、子孫繁栄
【八つ頭】
頭となって出世をするように、子芋がたくさんつくので子孫繁栄
【くわい】
大きな芽が出て「めでたい」、子球がたくさんつくので子孫繁栄
【ごぼう】
根を深く張り代々続く


いかがでしたか。
今のように冷蔵庫がなかった時代、本来のおせち料理は、保存がきくお料理がほとんどです。
日持ちがするという理由以外にも、年神様に静かに過ごしていただくため、台所で騒がしくしないという心配りも含まれていました。
また、かまどの神様に休んでいただくためや、神聖な火を使うのを慎むためともいわれています。
そして、年末年始、多忙な女性が少しでも休めるようにという配慮もあったかも知れません。
現代のおせちは、家族の好みのものを中心に、洋風や中華風の料理が入ったり、サラダのような生野菜が加わったりと、とても多彩になりましたが、先人のこうした知恵と心を大切にしながら、素敵な正月を迎えたいものですね。

お電話でのお問い合わせ 0120-93-4568
営業時間 9時~18時 [定休日・日曜]
香川県高松市牟礼町大町1392番地2
mail : ex_kishishita_1392_2@yahoo.co.jp
11月に入りましたね!
今年も残すところ・・・あと2か月。
10月30日に発信しましたおせち料理の第2段

弐の重のまめ知識です


弐の重[焼き物]
縁起のいい海の幸が中心です。
【ぶり】
ぶりは大きさによって名前が変わる出世魚。ぶりで立身出世を願います。

【鯛】
「めでたい」にかけています。
姿もよく味もよい鯛は、江戸時代から「人は武士、柱は檜(ひ)の木、魚は鯛」といわれ、めでたい魚として祝膳には欠かせないものとされています。

【海老】腰が曲がるまで長生きできるように。

参の重[煮物]
山の幸を中心に、家族が仲良く結ばれるよう煮しめます。
【れんこん】
穴があいていることから、将来の見通しがきくように
【里芋】
子芋がたくさんつくことから、子孫繁栄
【八つ頭】
頭となって出世をするように、子芋がたくさんつくので子孫繁栄
【くわい】
大きな芽が出て「めでたい」、子球がたくさんつくので子孫繁栄
【ごぼう】
根を深く張り代々続く


いかがでしたか。
今のように冷蔵庫がなかった時代、本来のおせち料理は、保存がきくお料理がほとんどです。
日持ちがするという理由以外にも、年神様に静かに過ごしていただくため、台所で騒がしくしないという心配りも含まれていました。
また、かまどの神様に休んでいただくためや、神聖な火を使うのを慎むためともいわれています。
そして、年末年始、多忙な女性が少しでも休めるようにという配慮もあったかも知れません。
現代のおせちは、家族の好みのものを中心に、洋風や中華風の料理が入ったり、サラダのような生野菜が加わったりと、とても多彩になりましたが、先人のこうした知恵と心を大切にしながら、素敵な正月を迎えたいものですね。
お電話でのお問い合わせ 0120-93-4568
営業時間 9時~18時 [定休日・日曜]
香川県高松市牟礼町大町1392番地2
mail : ex_kishishita_1392_2@yahoo.co.jp